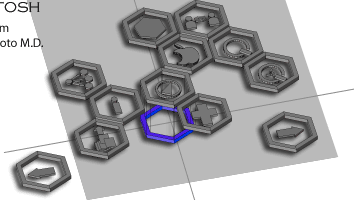|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top > medical > medical record system ▼NAV ▼form ←Previous Next→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
812_ the wide-window concept
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
既存の紙の書類をメタファーにすることで、自然な入力を目指しました 医療現場での「伝票」や「用紙」といった既存の書類を画面に再現し、必要部分を埋めていくようなインターフェースを多く採用し、新たに覚える必要を極力減らしています。 |
画面の色を紙の伝票と統一させることで統一感を持たせています。たとえば血算データは赤、生化学データは青系、培養データは黄土色など。 テンプレート機能を持たせセット登録を可能としました。 これまでの「セットはんこ」や「病名印」に近い発想でテンプレート機能を持たせています。 |

814_ summarize |
要約の自動作成 外来で忙しいなか、入院概要をひとめで把握する必要に迫られることはよくあります。入院概要をワープロ化することで可読性は上昇しますが、どうしても冗長になりがちです。そこで、経過表機能を持たせました。ファイルメーカーで任意の作図をすることはそれなりのプログラミングが必要ですが、その部分は完全に省略し、それよりも文章を解析し、使用薬品や治療の内容のパターンを分類認識させることに重点をおいて設計しました。「喘息の治療でステロイド静注が必要だったのか、酸素は、プ→ |
|
|
|
||
|
→ロタノール持続吸入をしたのか、しなかったのか」「ファーストチョイスの抗生物質はきいたのか、利かなかったのか」など、再度入院したときの参考になる経過情報が、ペーパー用図譜まではいかなくてもそれに近いクオリティで貼布されます。この機能を実現する上で、単語の統一が必要となります。入力する側に統一語彙の使用を強いるのではく、プログラム側に同義語辞書を内蔵することでより自由な表記を可能としています。 自動文章作成 たとえば、退院概要を記載した場合、それをもとに文章の必要な部 |
分を切り取り、定型文を前後に貼布して紹介状や紹介元への返事文章の雛形を作成する機能を持たせています。これには辞書機能を搭載し、院内のみ通用する略語を正式書体に変更することや、「です・ます」調への文体変更を実現しています。 データの貼布 検査データの転記など、単純作業は極力自動化しています。検査室などから出力される生データを分類し、必要なデータだけをブラウズし選択ボタンを押すだけで貼布するようになっています。貼布枠を制限することで、結果的に冗長なデータを減らします。 |
|
一度入力した情報は、できるだけ再度打ち込むことのないように配慮しました。リレーショナルデータベースをもとに作られていますが、それを徹底しました。たとえば、紹介元住所録は紹介者の氏名をプルダウンメニューの中から選択するだけで、組織、部署の報告書への表示にとどまらず、封筒印刷や紹介者別患者名簿の作成などを可能としています。外来受診時の次回予約画面の表示は、そのまま外来受診時間のサンプリングを初め、半自動的にデータを蓄積します。それらの情報はレセプト作成時に診察料算定ために使用されるだけでなく、予約に対しての待ち時間の評価や、当直等の当直記録の作成なども対応しています。 |
患者の住所、電話番号などの情報は、一見必要性の少ないようにも見られがち(もちろん緊急連絡用に必要ではあり、データベースとしての蓄積は必要)ですが、一歩進めて同居の家族、兄弟の受診予約データを表示するために使うことで、兄弟並診や「姉が今度受診することになっているのですが、一緒に予約できませんか?」というような場合にスムーズに対応できるようになっています。 |
リアルタイム情報としてデータがまだ入力されていないということも一つの情報として利用しています。受診しているのに次回予約や終了情報がないということは、緊急検査待ちや処置待ちの状態であることが予想されるわけです。画面にそれらの情報を明示することで、長く処置に時間がかかっているひと、検査を長く待っている人が常に分かるようになっています。診療支援データベースとしての役割検査データの分類検査データは数分で結果が出るものから1ヶ月かかる検査もあります。同時に結果のでない検査データを分類表示し、時系列としてコンパクトに表示することで、入院時検査と外来検査の連携をしやすいようになっています。 |
|
|
||
保険診療上の支援保険診療を進めていく上で、これまで医療事務として診療と分離されていた業務が、医師の業務となり、診療面での負担増となる傾向があります。特定疾患カウンセリングや養育指導などは時代の流れから、カルテへの内容の明記が必要になっています。算定が可能な指導料をリアルタイムに表示することで支援するだけでなく、月末に集計、一覧表示することも可能です。ファイル構成患者マスター患者マスターと呼ばれる、このファイルの目的は、患者本人のシリアルナンバーである病歴番号をもとに、氏名、読み仮名、住所、電話番号、各種指導料の開始年月日、などが収められるとともに、禁忌薬の情報なども収められています。 |
入院病歴名前のとおり、入院概要を主体とします。入院番号ないし退院番号を主に、入院病名、入院月日、退院月 日、概要本文、入退院にまつわる紹介状、報告書などの情報提供の内容を持っています。外来受診記録 外来受診日時、病名、処置内容、各種指導料算定用データが記録されています。このファイルの主な機能は外来予約であり、それ以外の情報は外来予約時に半自動的に取り込まれることで、最終的にはレセプト(保険点数計算)へとデータを持っていくことができます。
|
処方履歴主に退院処方について、管理しています。シリアル番号を工夫することで、同じファイルにテンプレート機能も持たせています。繰り返し入院する人に対し、処方履歴の再利用は入力の面で大変助かります。画像ベース入院病歴に連動した画像ベースです。ファイルメーカーのシステム上、データベース内部に画像を沢山持たせると処理スピードの面で問題が出てきます。もちろん、外部参照とするように記載することもできますがファイル名の管理や、アップルスクリプトとの連動を考え、現状ではファイルメーカーに画像ファイリングもさせています。紙の伝票との連携を図るため、アップルスクリプトの連動で、スキャナーから既存の書類の取 |
|
|
||
り込みを実現しています。古い入院サマリーや紹介状の返事などの紙の書類などをイメージとして保存分類し、貼布できるようになっています。紹介元(紹介先)住所録紹介元(紹介先)の先生の氏名、所属病院、所属科、住所、郵便番号、電話番号などの情報をもっています。紹介状の作成時に使用され、封筒の印刷などにも使用されます。概要作成用語彙辞書 薬剤一つをとっても、商品名や正式名、略語などいろいろな表記があります。それらの統一性を持たせるために辞書を内蔵し、ユーザーによっていつでも加えることが可能となっています。 経過表ベース |
経過表を表示するためのデータベースです。治療内容のパターンを認識、分類するようになっています。文体変換辞書紹介状や報告書の雛形を作成するとき、文体を「です」「ます」調に変更し、院内での略語などを正式な単語に変換するための辞書となっています。これもユーザーにより自由に拡張できるようになっています。 診療報酬データーベース 現在は基本診察料と指導料や管理料のみとなっていますが、年度ごとに変更される診療報酬の変更にも対応できるようにデータベースを持っています。 指導料を算定するに当たり、算定可能病名が存在します。これらのデータを持つことで、診療支援情報として外来受診時の画面に表示するために使用されています。 |
最後に実はこの一連のファイルは、私がファイルメーカープロを使ったはじめての事例でした。日常業務に柔軟に対応できる高い可塑性と、電子化がほとんど進んでいない現場では、紙書類と親和性の高いアプリケーションとして強い印象を持ちました。このスクリプトの一部は現在も病歴管理用として役立っています。現在は、診療支援システムを設計中です。医事会計由来の使い難い電子カルテのフロントで利用される、疾患に特化したサブシステムで、やはりファイルメーカーを利用しています。そちらの紹介も計画中です。 |

medical macintosh (c) 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006
Written/Edited by Y.Yamamoto M.D.
Privacy and Security Policy
ご自由にリンクして下さい。アップルおよびアップルのロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer,Inc.の登録商標です。POWERBOOK ARMYおよびmedical macintoshは、独立したユーザグループで、アップルコンピュータ株式会社が権限を与えた団体、支援する団体、またはその他に承認する団体ではありません。 |